
シンプルに書くこと×AI翻訳の活用
2024年10月、金沢にて開催された第33回JTF翻訳祭2024で、テクニカルライターとして、また英文の評価、指導などで活躍されている中村哲三さんが「情報を『つかう』『つたえる』視点で考えるAI翻訳活用法」というタイトルでご講演され、その後でお話しを伺いました。
シンプルに書くこと
石岡:これまで翻訳とライティングは個別の技術として考えられてきましたが、ChatGPTのような生成AIの登場で、AIツールにテクニカルライティングを学習させれば原文の品質を高めることができるし、翻訳文の品質をも高めることができる、という実践的なお話はとても有益でした。
そもそも伝わる文章にするためには、わかりやすい文章の組み立てが必要だし、読み手を意識することが重要で、そのためには簡潔に書くことだと。長い文章には句や節が多く、その句と節の間の係受けが曖昧になり、わかりにくくなるというわけです。複雑な係り受けや条件提示などを、漢字表記を全体の2~3割に、かつ20文字以内でまとめれば劇的にわかりやすくなる、というメッセージは目から鱗でした。
Chat GTPで「中学2年生でも理解できるように」とプロンプトを与えて、リライトすればかなり短くなってわかりやすい表現になることも納得です。伝えるためには「シンプルに書く」ことの重要性を、今日は改めて認識しました。
中村:文章が長くなる時は要点がわかっていないのでしょう。まず何を言いたいのか、それをはっきり把握していない。私も長くなったりします。短くまとめようとすることで文意もクリアになります。

この先、AI翻訳と共存していくために
宮脇:MTだけでなく、ChatGPTの翻訳レベルは劇的に向上しています。それでもそれがプロの翻訳文として使いものになるか、と抵抗感を持っていらっしゃる方もまだたくさんいると感じます。私自身もどちらかというとそうした考えを持っていましたが、今回の講演を聞いて、目的や読み手によって文体を変えることができるし、特にChatGPTは使い方によってかなり文章の品質向上に役立つ、とポジティブに捉えられるようになりました。
翻訳者がMTやChatGPTと上手く共存していくために、「こういう使い方をした方がいいのでは」とお考えは何かありますか?
中村:まずはセキュアな環境で使うことが前提ですが、背景情報を調べたり、読み手を指定して読みやすい文章にするなど、便利なツールは、とにかく使って、自分の能力のひとつにすることです。自分の能力として使いこなし、こちらが使われてしまわないよう、注意が必要です。

宮脇:(AIの回答を鵜呑みにせず)わからないことや、腑に落ちない回答が返ってきたら、詳細まで踏み込んで質問したり、プロンプトで「わからない場合は、『わからない』と答えてほしい」と指定するのもありですか?
中村:そうです。使う側も、むやみに信じないことです。ChatGPTも、翻訳で間違ったりします。まだ、そこまでのレベルではありませんが、そのうち人間を超える時は来るでしょう。今の段階では、少なくとも主役は「自分」ですから、ChatGPTはその便利ツールとして考えるということが大事です。

MTやChatGPTに期待しすぎてもいけないし、期待しないのもいけない。でもせっかくのツールですから、これを仕事の場で使っていけるようになるほうがいいし、使えたほうが、他者と比べて強みになります。ビジネスとしてやっていくには、属人的なものは基本的に捨てていかなければいけないと思います。
終わりに
内容を伝えるために、文章はなるべくシンプルであること。そのためにAIの力を借りることは、今後共存していくための1つの重要な道だと感じました。使用する側が主導権を持つことを軸に、様々な可能性を秘めたAIと共存できる方法を、私たちPMの立場でも探っていきたいと感じました。
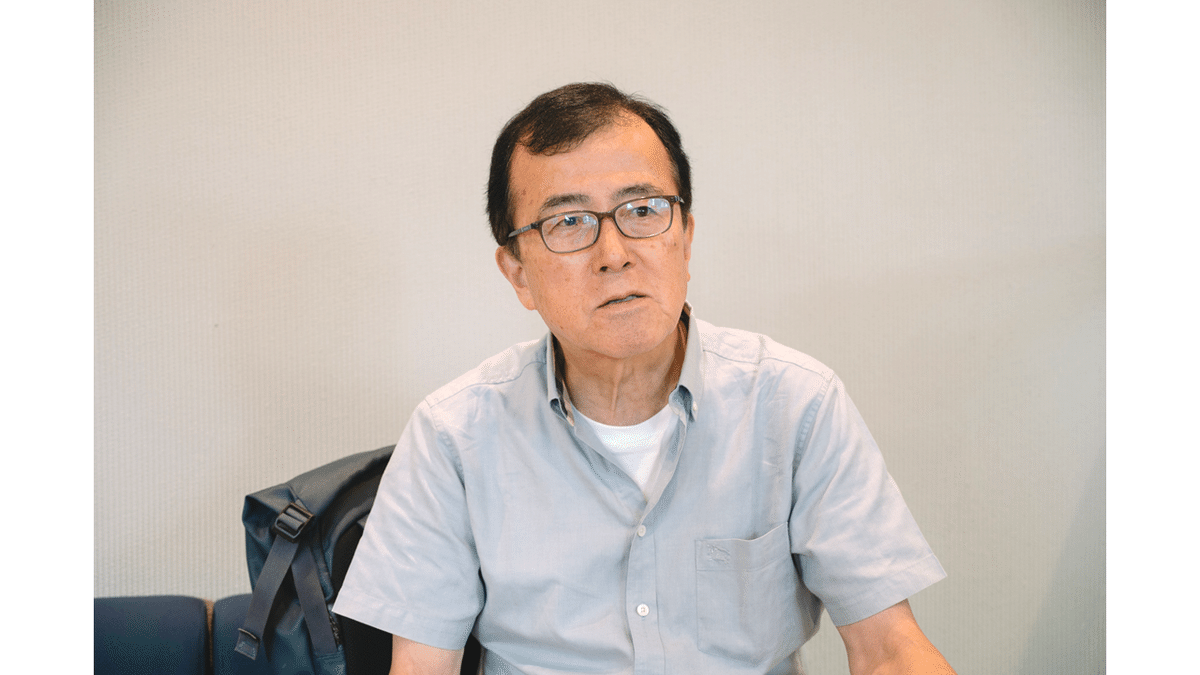
中村 哲三
テクニカルライター
株式会社エレクトロスイスジャパン 英文ドキュメント評価・改善担当
ASD-STE100 (AeroSpace & Defence Simplified English) STE Maintenance Group (辞書編纂委員) トレーナー
ISO TC37 (Language Resources) 委員
聞き手:石岡 映子/宮脇 萌(株式会社アスカコーポレーション)

